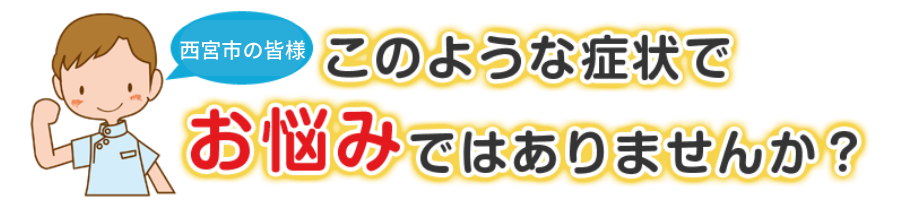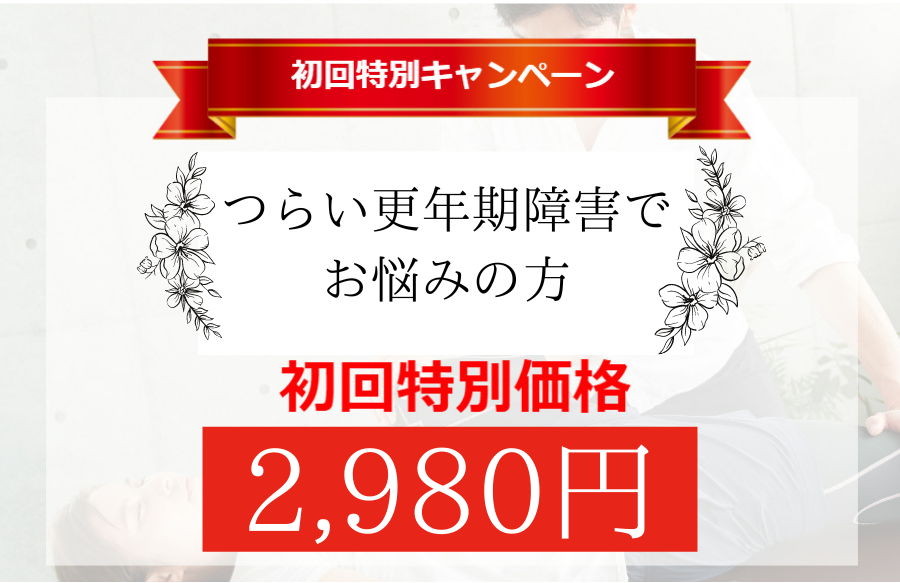- 動悸
- 息切れ
- 不眠症状
- 疲れやすい、疲れが抜けない
- イライラ
- 意欲の低下
- 不安感
- うつ症状
- のぼせ、ほてり(ホットフラッシュ)
- 発汗
- 肩こり
- 頭痛
- めまい
- 腰痛
- 肥満
- やせ
- 嘔吐
などが挙げられます。
ご覧の通り、更年期障害の症状は本当に多岐にわたります。
しかも、上記はほんの一例であり、他にもたくさんのものが存在します。
更年期に入って初めて感じるような症状もあるため、
「今までこんなことなかったのに…」
と精神的にも辛い状態に陥るケースもあります。
更年期障害とは?
更年期とは、閉経に伴う前後10年ほどの期間のことを指します。
日本人女性の場合、平均的な閉経年齢が50歳ぐらいと言われていますので、およそ45〜55歳ぐらいの時期のことを更年期と呼ばれています。(閉経の時期には個人差があるため、多少は前後します。)
この時期に起こりやすい不定愁訴などを含め、更年期障害と呼ばれています。
更年期障害がおこるメカニズム
更年期障害が起こるメカニズムについてご紹介していきます。
更年期障害は、閉経に伴う女性ホルモンの分泌減少によって起こると言われています。
女性ホルモン(中でもエストロゲン)が減少すると、それまで統括されていた身体の機能がバランスを崩してしまいます。
女性ホルモン自体は卵巣から分泌されますが、その分泌の司令塔は脳です。
女性ホルモンの減少を察知した時に、「おーい、もう少し分泌を増やしてよー」と脳から命令が出ますが、閉経の時期はそのような連携がうまく取れなくなってしまいます。
その際に起きる脳の異常な興奮などから、更年期障害の様々な症状を引き起こしてしまうとも言われています。
まとめると、更年期障害は身体が急な変化に対応できずに不調をきたしている状態です。
病院での治療法
病院での更年期障害の治療についてご説明していきます。
病院での更年期障害の治療法としては以下のようなものがあります。
- ホルモン補充療法
- 漢方薬の処方
- 抗うつ剤、抗不安薬の処方
それぞれ解説していきます。
【ホルモン補充療法(HRT)】
更年期で減少する女性ホルモン(エストロゲン)を補充する治療法です。
子宮がある場合は、エストロゲンと黄体ホルモンを併用することが多く、子宮がない場合はエストロゲンがメインで扱われます。
補充の方法としては、飲み薬・貼り薬・塗り薬のタイプが存在します。
基本的には毎日服用する必要があり、貼り薬の場合は数日に一度貼り替える形となります。
【漢方薬】
体質に合わせて漢方薬を処方することがあります。
漢方の処方の際には「四診(ししん)」を用いて、脈や舌・腹部などの診断を行い体質を判断していきます。
更年期障害の際によく処方される漢方としては、
- 加味逍遙散(かみしょうようさん)
- 温経湯(うんけいとう)
- 五積散(ごしゃくさん)
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 温清飲(うんせいいん)
- 当帰芍の花薬散(とうきしゃくやくさん)
などがあります。
体質改善の治療であるため、体調の変化が出るまでにはしばらく期間がかかるケースが多いのも特徴のひとつです。
【抗うつ剤、抗不安薬】
不安感や意欲の低下(うつ症状)・イライラなど、精神症状を抑えるために抗うつ剤や抗不安薬が用いられることがあります。
更年期障害ではメンタルケアも重要となるため、薬物療法以外にもカウンセリングなどを勧められるケースも。
一人で抱え過ぎないことも、更年期を乗り越えるための大切な要素です。
こうのとり治療院の治療法は?
体液循環と体液の質を良くすることを目的としています。
体液循環とは?
血液、リンパ液、脳脊髄液などの循環のことです。
循環が悪くると、各細胞までエネルギーが届かず、細胞の元気がなくなってしまします。
また、ホルモンの循環が悪なってしまうので、身体が正常に働かなくなってしまいます。
体液の質とは?
主に血液の質を指します。
血液の中にしっかり栄養が入っているかどうかが、身体の状態に大きく影響します。
内臓整体
内臓は、消化吸収に関わります。
消化吸収が悪くなると、血液の質が悪くなってしまいます。
自律神経の調整
自律神経の乱れが更年期障害の症状の主な原因です。
自律神経を整えるために、頭蓋骨の調整・鍼灸・背骨の調整などで自律神経を整えていきます。
栄養指導
基本的には、「栄養不足」というのが更年期障害にはあります。
何の栄養が足りないのか?何を摂りすぎているのか?
などを、細かく聞き取りながら、必要であればサプリメントなどを活用して改善していきます。